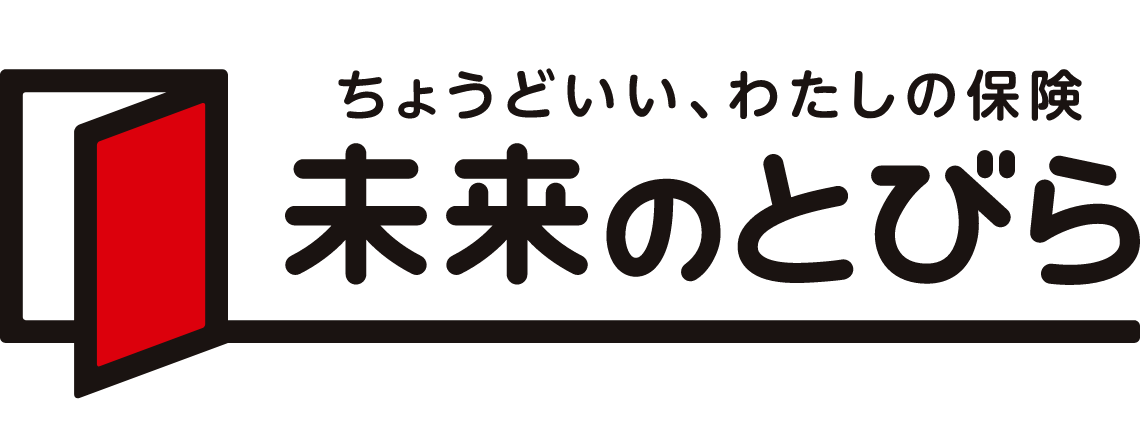保険お役立ちコラム
生存給付金付定期保険とは?一般的な定期保険との違いやメリット・デメリットを解説

契約期間に定めのある定期保険は、基本的に掛け捨て型の保険ですが、一定期間ごとに生存給付金が受け取れるものもあります。生存給付金が付いている定期保険を選ぶことで、万一の場合に備えつつ、定期的に給付金を受け取ることができます。
ただし、メリットだけでなくデメリットも存在しているため、誰にでも向いた保険商品とは必ずしも言い切れません。この記事では、生存給付金付定期保険とは何なのか、一般的な定期保険との違いに触れつつ解説します。
目次
1.生存給付金付定期保険とは

生存給付金付定期保険は、一言でまとめると「加入者が生きていれば定期的に給付金が受け取れる」タイプの定期保険です。以下、生存給付金付定期保険について、基本的なプランの内容に触れつつ解説します。
生存給付金とは
生存給付金は、保険期間中に“加入者が生存していれば”一定期間ごとに受け取れる給付金のことをいいます。生存給付金には他にも複数の別称があり、保険商品によって祝金・健康祝金・生存祝金・無事故祝金などの名称で呼ばれることがあります。
一般的に、生存給付金がプランに含まれる定期保険は「生存給付金付定期保険」と呼ばれ、終身保険・医療保険でも生存給付金を受け取れる商品があります。万一のことを考えて定期保険に加入しようと考えているものの、自分が生きている間の備えも充実させたい方にとって、生存給付金付定期保険は最適な保険商品のひとつといえるでしょう。
生存給付金の受取りイメージ
生存給付金は、満期を迎えたら一定額のお金が受け取れるタイプの給付金ではなく、年単位で給付されるタイプの給付金です。たとえば、保険に加入してから「5年ごとに5万円」といったタイミングで、一定額が生存給付金として給付されるようなイメージです。
ただし、すべての商品で5年という縛りが設けられているわけではありません。受取りのタイミングが3年ごとになっている商品もあれば、3年・5年など希望の期間を自分で設定できるものもあります。保険会社で期間があらかじめ設定されている商品もあるため、複数の商品を比較検討する際は、給付金の受取り方についてもチェックしましょう。
そのほか、満期時に「満期お祝い金」などという形で生存給付金が割増でもらえる商品もあります。自分の欲しいタイミングにあわせて商品を検討するのはもちろん、満期時にもらえる給付金の額にも注目しましょう。
引き出すタイミングを選べる商品もある
生存給付金は、原則として一定期間が経過しないと受け取れないタイプの給付金ですが、受け取るタイミングで特に使用目的が思い浮かばない場合は、給付金を受け取らずにすえ置ける商品もあります。
そういった商品の場合、生存給付金を必要なときに引き出すことができます。車が必要になったとき、子どもの進学でまとまったお金が必要なときなど、用途を問わずお金を引き出せます。なお、引き出していない生存給付金には利息が付くため、貯蓄のような感覚で活用することもできます。
2.一般的な定期保険との違い
一般的な定期保険は、契約時に定めた一定の期間を保障する内容の保険で、契約期間中に死亡または高度障がいになった場合に保険金が支払われます。そのため、解約時の解約払戻金に関しては「ゼロ」またはごくわずかという商品が多く、その分だけ割安な保険料で保障を受けられるという特徴があります。
これに対して生存給付金付定期保険は、定期保険の特徴を備えつつも、加入者が生存している間は定期的に生存給付金が受け取れる仕組みです。その分保険料は高くなる傾向にありますが、一般的な定期保険と比べて貯蓄性が強い保険商品のため、保障と貯蓄を両立させたい方には向いています。
まとめると、一般的な定期保険と生存給付金付定期保険との違いは、加入者が生きている間の備えが充実しているかどうかです。保険加入を検討している段階で健康に特段問題が生じていない方や、掛け捨て型の保険に抵抗のある方は、生存給付金付定期保険への加入を前向きに考えてもよいでしょう。
生存給付金付定期保険の加入前に考えたいこと
詳しいメリット・デメリットは後述しますが、生存給付金付定期保険は、万一の備えに加えて将来の蓄えにもなる商品です。加入することで生存給付金を受け取るというモチベーションが得られるため、普段の健康により気を遣うようになったり、給付金を受け取った際の使い道を想像して考え方がポジティブになったりするかもしれません。
しかし、一般的な定期保険に比べて保険料は高くなる傾向にあるため、保険料を抑えたい方にとっては掛け捨ての方が望ましいかもしれません。生存給付金付定期保険に加入すべきかどうかは、その人のライフスタイルや保険商品に期待することによって変わってくるため、加入前に十分検討することをおすすめします。
3.生存給付金付定期保険のメリット
生存給付金付定期保険は、自分に何かあった場合だけでなく「自分が元気に過ごすことができた」場合も想定して加入できるため、健康に自信がある方にもおすすめの商品です。以下、加入者が得られる主なメリットをまとめました。
定期的にお金が受け取れる
掛け捨ての定期保険に加入した場合、基本的に支払ったお金は手元に戻ってきません。しかし、生存給付金付定期保険に加入すると定期的に生存給付金が受け取れるため、さながら「ミニボーナス」感覚でお金が手に入ります。
終身保険や養老保険・学資保険などの貯蓄型保険に比べると、月々の保険料負担も少ない傾向にあり、貯蓄型保険は無理でも自分が生きている間に備えが欲しいと考えている人には向いています。商品によっては満期時になると生存給付金が割増でもらえますが、その前にも3年・5年など一定のタイミングで定期的に生存給付金が受け取れるため、ライフイベント発生と給付のタイミングを考えたうえで加入することができます。
たとえば、結婚後に生存給付金付定期保険に加入する場合、子どもが3歳(幼稚園入園)の時に加入し、8歳、13歳、18歳(大学入学)と5年ごとに受け取れるような商品を選んでもよいでしょう。これまで頑張ってきた自分へのごほうびとして、生存給付金を自分の趣味や旅行などの楽しみのために使うのも、魅力ある生存給付金の使い方といえます。
受け取るかすえ置くか選べる
生存給付金付定期保険は、一定の期間ごとに生存給付金を受け取れますが、そのタイミングで必要なければすえ置くことができます。そして、受け取らずにすえ置いた分には利息が付き、必要になった場合は引き出せるため、保険商品にもかかわらず普通預金のような自由度があります。
将来の備えがむずかしい人向き
生存給付金付定期保険は、貯蓄型保険よりも安価に保障と貯蓄を両立できるため、将来の収入額を具体的に予想できない方にも適しています。自営業の方など、収入が不安定でなかなかお金を貯められず悩んでいる方は、保障と貯蓄を両立させる生存給付金付定期保険に加入しておくと安心です。
ちなみに、契約者が生存給付金を受け取った場合、原則として「一時所得として他の所得と合算」したうえで所得税・住民税が課税されます。しかし、通常は実際に払い込んだ保険料の金額が生存給付金の金額を上回るため、受け取った時点では課税されないことがほとんどです。
4.生存給付金付定期保険のデメリット
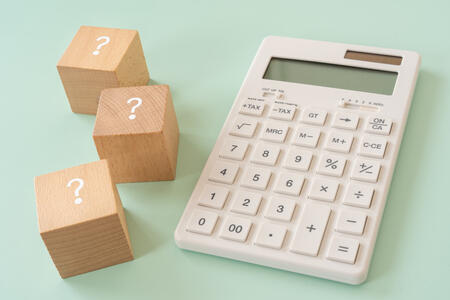
生存給付金付定期保険は保障と貯蓄を両立できるというメリットがありますが、一方で以下のようなデメリットも想定されるため、実際に加入する際はよく検討しましょう。
保険料負担が大きくなる
一般的な定期保険に比べて、生存給付金付定期保険の保険料はどうしても高くなりがちです。そのため、プランによっては毎月の家計を圧迫するおそれがあります。
一定のタイミングで生存給付金が得られるとしても、月々の支払いが苦しいようでは、保険加入のメリットは小さいでしょう。保険加入の際は、毎月支払っても生活に支障がない保険料の範囲で商品を検討しましょう。
貯蓄重視の場合は向かない
生存給付金付定期保険は、基本的に「支払った保険料の総額」以上の生存給付金を受け取れない仕組みとなっています。よって、万一の保障よりも貯蓄を重視するのであれば、生存給付金付定期保険を選ぶべきかどうかは判断が分かれるところです。
将来に備えるため、あくまでも貯蓄額を重視する方にとっては、定期預金や他の投資商品などを検討した方がよいでしょう。逆に、保障重視でそこに貯蓄をプラスしたいと考えている方は、生存給付金付定期保険に加入するメリットが大きいものと考えられます。
税金がかかるケースに注意が必要
「保険料の支払人」と「生存給付金の受取人」が異なる場合、贈与税が発生するおそれがあります。たとえば、生存給付金を受け取るのが加入者本人ではなく、配偶者だった場合などが該当します。
贈与税の基礎控除額は、生存給付金以外の贈与も含め、年間で110万円までとなっています。そのため、毎年贈与を行っている場合は注意が必要です。また、すえ置いた生存給付金の利息は、所得税の雑所得として課税対象になる点にも気を付けましょう。
5.まとめ
生存給付金定期保険は、加入者に万一のことが起こった場合だけでなく、加入者が元気に生きている場合にも給付金が受け取れるタイプの定期保険です。生存給付金は、3年・5年といった一定のタイミングで受け取る商品が多く見られますが、すえ置くことによって引き出すタイミングを自分で選ぶこともできます。
ライフイベントに備えるほか、自分へのごほうびとして使うなど、生存給付金の使い道は人それぞれです。収入が不安定な自営業者の場合、将来への備えと貯蓄を両立させられるメリットもあります。ただし、定期保険に比べて保険料は高くなる傾向にあるため、無理なく支払いができる商品・プランを選ぶことが大切です。
なお、フコク生命「未来のとびら」の、「生存給付金付定期保険特約」もご検討ください。
2025年04月15日
カテゴリ
キーワード
資料請求・ご相談