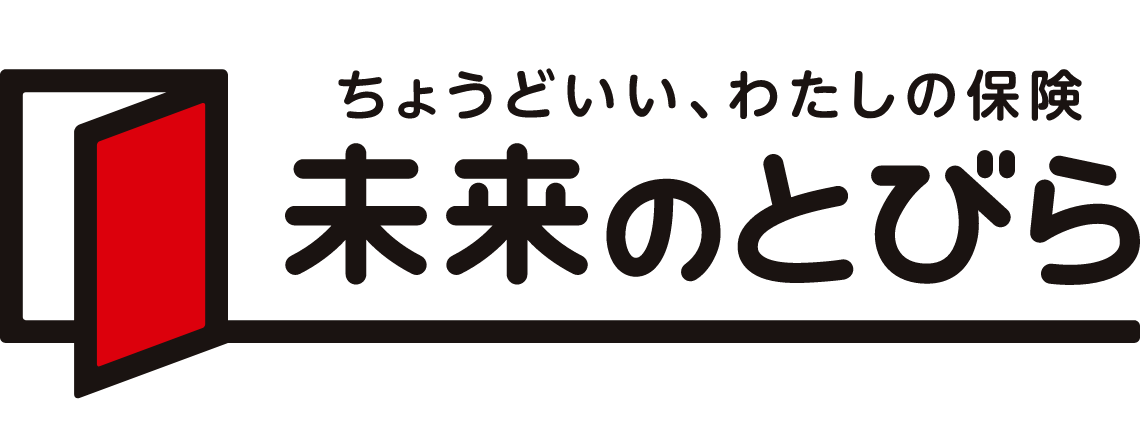保険お役立ちコラム
脳卒中に保険で備えるためには?三大疾病保障や発病後でも入れる保険についても解説

目次
2023年の厚生労働省の人口動態統計によると、脳血管疾患(以下、脳卒中)は日本人の死因の第4位となっており、実に10万人以上が亡くなっています。
運良く脳卒中から回復しても、失語症や失明などの後遺症が残るおそれがあり、治療やリハビリにもお金がかかります。
脳卒中のリスクに関しては、三大疾病保険などの各種保険に加入しておくことで、治療費の負担や長期入院中の収入減にそなえることができます。
この記事では、脳卒中にそなえられる保険として、三大疾病保障や発病後でも入れる保険について解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
※ 本記事では、一般的な例を記載しています。本記事で言及している保険商品・保障内容等について、当社では取扱いの無い場合がございます。
詳細は取扱いのある金融機関にお問合わせください。
1.脳卒中について

脳卒中は、がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞とあわせて「三大疾病」と呼ばれ、日本人の三大死因とされています。
まずは、脳卒中の症状について解説します。
脳卒中とは
脳卒中とは、脳の血管がつまったり破れたりすることで、脳の働きに障害が起きる病気です。
人間の身体の働きを中枢で統括している脳の血管がダメージを受けるため、脳がつかさどっていた機能が失われ、最悪の場合は死に至ることもあります。
卒中とは「卒然として中(あた)る」の意味で、昔から突然身体が動かなくなり倒れるような病気があったことは知られており、一部地域では脳卒中のことを「あたった」といいます。
それだけ強烈なダメージを身体に与えるため、日本人にとっては注意したい病気のひとつです。
脳卒中になってしまう主な原因は、心臓や全身をめぐる血管にダメージが蓄積してしまうことです。
具体的には、肥満や糖尿病・高血圧症といった生活習慣病などが引き金となって、最終的に脳の血管がやられてしまうのです。
脳卒中になってしまうと、半身まひや言語障がい・意識障がいといった形で、後遺症が残ることもあります。
回復にも時間がかかり、普段の生活にも影響がおよぶことが予想されますから、長期の治療・療養にかかる費用にそなえるためにも保険への加入は重要です。
脳卒中に含まれる病気
脳卒中は、正式には脳血管障害という名前で呼ばれる病気で、ひとつの病名ではありません。
具体的には、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の3種類が含まれます。
以下、それぞれの病気の症状についてご紹介します。
脳梗塞
脳梗塞とは、脳の血管がつまってしまい、血流が十分に脳細胞にいきわたらなくなる病気のことをいいます。
脳卒中と聞いて、脳梗塞をイメージする方は多いのではないでしょうか。
脳梗塞になると脳の動脈が閉塞するため、血液が行き届かなくなった脳は、数時間経過すると壊死してしまいます。
脳梗塞によって残る後遺症の種類としては、以下のようなものがあげられます。
- ●
片方の手足のまひ、しびれ
- ●
ろれつが回らない
- ●
言葉が出てこない
- ●
視野が欠ける
- ●
めまい
- ●
意識障害
脳梗塞は、症状がひどくなる(劇症化する)前に発見されるケースが多く、脳梗塞によって亡くなる例は少ない傾向にあります。
国立循環器病研究センターの推定によると、脳梗塞患者の30日以内の院内死亡率は4.4%となっていて、決して致死率が高い病気ではありません。
しかし、後遺症が残ったまま生活を続けるのは大変ですし、リハビリにも時間がかかります。
これまで続けてきた仕事を続けられなくなる可能性もありますから、生活資金の確保という観点から、保険に加入しておくメリットは大きいでしょう。
脳出血
脳出血とは、脳内の細い血管が裂けてしまい、脳組織の中に直接出血してしまうことをいいます。
発症にあたり「前触れの症状がない」ことが特徴のひとつで、ある日突然発症してしまうおそれがあります。
脳出血は、脳梗塞よりも後遺症が残りやすく、死亡率も高くなります。
国立循環器病研究センターの推定によると、脳出血患者の30日以内の院内死亡率は16.0%となっていて、脳梗塞のおよそ4倍にまで死亡リスクが上昇しています。
脳出血の大きなリスク因子のひとつに、長年の高血圧があげられます。
高血圧によって、脳内の細い血管がもろくなると、その一部が膨らんで小さなコブができます。
その状態でさらに高血圧が続くことにより、血管が破裂して脳内に出血するのです。
このような病状は「高血圧性脳出血」と呼ばれ、脳出血の主な原因となります。
脳出血になるリスクを減らすためには、高血圧の予防・治療が有効です。
脳に関連する疾患が原因の脳出血に関しては、原因となる疾患の治療を行わないと、再発する危険性が高くなります。
回復までに時間を要することが予想されますから、公的医療保険でまかなえない医療費の自己負担額を軽減するためにも、保険加入を検討したいところです。
くも膜下出血
くも膜下出血とは、脳動脈瘤が破れることで、突然の頭痛・意識障害などの症状が出現する病気のことです。
脳動脈瘤とは、脳内部の中~小動脈(径1~6mm)に発生する、こぶ状のふくれた部分のことをいいます。
脳動脈瘤が破裂すると、脳の表面を覆う「くも膜」という薄い膜の内側に出血します。
出血の程度が大きく、脳全体に強いダメージを与えることから、昏睡状態・突然死のリスクも高いのが特徴です。
くも膜下出血は重度の脳卒中に分類され、死亡率も高い傾向にあります。
国立循環器病研究センターの推定によると、くも膜下出血患者の30日以内の院内死亡率は26.6%となっていて、死亡リスクは脳梗塞のおよそ6倍・脳出血のおよそ1.7倍となっています。
一度裂けて出血した脳動脈瘤は再び出血しやすく、2度目の出血によって死亡することもあります。
脳卒中をカバーする保険商品の中には、保険金を複数回受け取れるものもありますから、将来のくも膜下出血にそなえて保険に加入しておくと安心です。
2.脳卒中にそなえる保険「三大疾病保障」について
まだ脳卒中の症状が出ておらず、高血圧などリスクとなる病気を持っている方は、保険で万一の状況にそなえる選択肢があります。
以下、脳卒中にそなえる保険の代表的な種類「三大疾病保障」についてご紹介します。
三大疾病保障保険とは
三大疾病保障保険とは、以下の病気(三大疾病)を発病してしまった場合に、所定の条件で保険金が受け取れるタイプの保険のことです。
- ●
脳卒中
- ●
がん(悪性新生物)
- ●
急性心筋梗塞
三大疾病のいずれかを発症した際に、支払条件を満たしている場合は、一時金として保険金が受け取れます。
また、死亡・高度障害状態になった場合に、死亡保険金または高度障害保険金が受け取れる商品もあります。
がん保険との違いについて
三大疾病保障保険との比較対象となる保険の一種として、がん保険があげられます。
三大疾病保障保険とがん保険には、次のような違いが見られます。
三大疾病保障保険
三大疾病保障保険は、脳卒中・がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞のすべてにそなえることができます。
がん保険に比べてカバーできる範囲が広いため、安心して加入できるのがメリットです。
デメリットとしては、各疾病につき、詳細な支払事由が異なる点があげられます。
たとえば、脳卒中でない脳血管疾患の場合に、保険金がもらえない可能性があります。
また、保障対象が広い分、保険料も高くなりがちです。
がん保険
がん保険は、がんの経済的リスクに特化している分、割安な保険料で万一にそなえられます。
診断一時金・治療給付金・入院保険金・手術給付金など、がんになった場合に給付されるお金の種類が多いのもメリットです。
しかし、契約後まもなくがんと診断された場合など、契約が無効になるケースもあります。
がんに特化した保険内容となっているため、脳卒中や急性心筋梗塞になってしまった場合は、保険金を受け取ることはできません。
三大疾病保障保険の注意点
三大疾病保障保険への加入を検討する際は、支払事由を確認しておくのが重要です。
商品によって詳細は異なるものの、三大疾病保障保険の支払事由は、保険会社によって以下のような違いが見られます。
| がん(悪性新生物) | 上皮内新生物を含むかどうか |
|---|---|
| 急性心筋梗塞(心疾患) | 急性心筋梗塞のみか、それともすべての心疾患が対象か |
| 脳卒中(脳血管疾患) | 脳卒中のみか、それともすべての脳血管疾患が対象か |
上皮内新生物とは、上皮細胞とそれ以外を分ける境界にある膜(基底膜)を超えずに、上皮細胞でとどまっているものをいいます。
上皮内新生物は、手術で完全に取り除くことで完治が見込め、再発リスクも低いと考えられています。
よって、上皮内新生物を保障の範囲に含めず、保険料を安くする選択肢もあります。
急性心筋梗塞や脳卒中も同様で、カバーする範囲を広げるかどうかによって、保険の選び方が変わってきます。
保険会社が取り扱う商品につき、より詳細な条件を確認すると、以下のような支払事由の違いも見られます。
- ●
支払条件に入院が含まれているかどうか
- ●
支払条件に該当する入院日数が定められているかどうか など
保険商品を選ぶ際は、加入を検討している保険会社の商品について、支払事由を丁寧に確認しておきましょう。
3.脳卒中の治療歴があっても入れる医療保険とは
脳卒中の再発リスクは、発症後1年で約12%、5年間で約35%にものぼります。
大前提として、脳卒中の治療を受けた人は、重い病気の発症経験・持病がある人と同じく通常の医療保険に加入するのはむずかしい傾向にあります。
ただ、脳卒中を治療した人が新たに保険に加入するための選択肢はゼロではなく、症状や治療状況によっては加入できる保険の種類もあります。
しかし、保険料が高くなったり制限があったりするため、できれば少しでも若いうちに保険加入しておくのがベターです。
以下、脳卒中の発症歴がある人でも加入しやすい医療保険について、主なものをいくつかご紹介します。
医療保険(一定の条件が付加されたもの)
一般的な医療保険の中には、保険料の割増や受け取れる保険金の削減といった条件を付加することで、病歴があっても加入できる保険があります。
しかし、特定の病気や身体部位につき保障の対象外とする条件もあるため、加入時には条件をよく確認しましょう。
引受基準緩和型医療保険
引受基準緩和型医療保険とは、加入時の条件が通常の医療保険よりも緩和された医療保険のことをいいます。
健康告知の内容がシンプルなため、少ない項目をクリアするだけで加入できるのがメリットです。
ただし、こちらも保険料が高かったり、給付金額が少なかったりするおそれがあります。
無選択型・無告知型保険
無選択型・無告知型保険とは、健康状態についての告知・医師による診査が保険加入時に不要な医療保険のことです。
病歴・年齢制限によって、通常の医療保険に加入できなかった人が主な対象者になります。
加入する際は、保険金の給付がなされない「免責期間」が、加入から一定期間設けられている点に注意しましょう。
4.まとめ
脳卒中は、日本人にとって発症するリスクが高い病気のひとつです。
脳卒中になる前に三大疾病保障保険に加入することで、長期にわたる治療を安心して受けることができます。すでに脳卒中を発症している場合でも、加入できる保険があります。
しかし、将来のことを考えて、できるだけ若い時期に保険に加入することをおすすめします。
フコク生命の医療保険「ワイド・プロテクト」などもご検討ください。

2025年04月16日
カテゴリ
キーワード
資料請求・ご相談