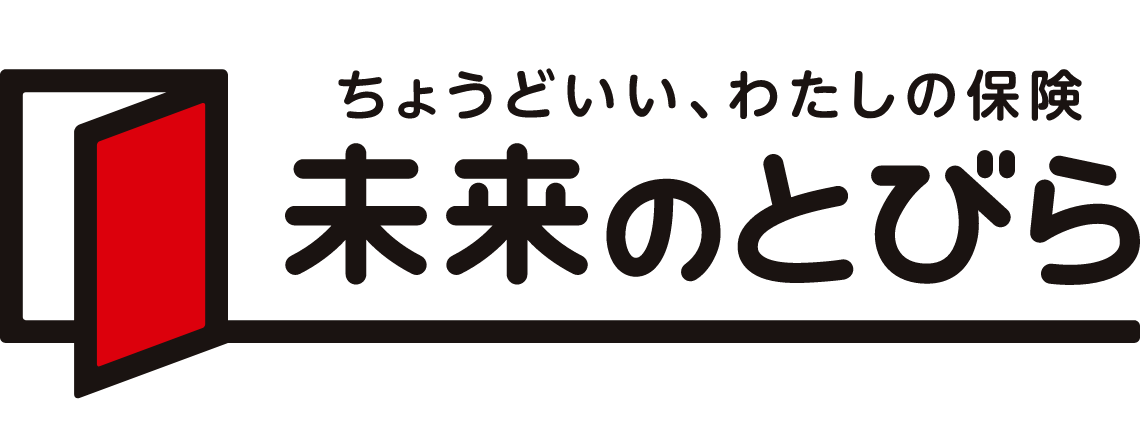保険お役立ちコラム
【就業不能保険】就業不能状態や支払条件に該当するのはどんなとき?

この記事では就業不能保険における一般的な就業不能状態とはどんな状態なのか?また、支払条件についてを具体的に解説します。実際に給付金の支払対象になった事例も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
- ※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。 - ※また、本記事では一般的な例を記載しています。本記事で言及している保険商品・保障内容等について、当社では取り扱いの無い場合がございます。
- ※本記事で紹介している就業不能保障特約「はたらくささえプラス」は特約組立型総合保険「未来のとびら」に付加できる特約です。
就業不能保険の支払条件を3つの視点で理解しよう

就業不能保険の支払条件は保険会社によって異なりますが、まずは、3つの視点から一般的な支払条件について解説します。
※フコク生命の就業不能保障特約「はたらくささえプラス」の支払条件とは異なります。
①支払対象になる就業不能状態とは?
就業不能保険は、病気やケガで働けなくなったとき、つまり就業不能状態になったときに給付金が受け取れる仕組みです。
では、就業不能状態とはどのような状態なのでしょうか。主な就業不能状態は以下のとおりです。
- ● 入院している状態
- ● 在宅療養している状態
- ● 障害等級1級または2級に認定された状態
それぞれの状態について、詳しくみていきましょう。
入院している状態
就業不能保険が適用される就業不能状態のうちの一例は、病気またはケガで、治療を目的として病院や診療所に入院している状態です。
厚生労働省の「令和2年(2020)患者調査の概況」によると、在院日数は年々減っているものの、令和2年の時点で病院は33.3日、一般診療所は19.0日。年齢階級別に見ると、65歳以上の平均在院日数は長くなる傾向にあります。※1
- ※1出典:厚生労働省「令和2年(2020)患者調査の概況」
在宅療養している状態
医師の指示により、自宅等で在宅療養している状態も就業不能保険が適用される場合があります。
在宅療養にあたるのは、病気やケガにより公的医療保険制度で在宅患者診療・指導料(往診料および緊急搬送診療料を除く)に記載されている医療点数が算定されているケースです。
また、加入している就業不能保険によっては特定の疾患になり、医師の指示のもと自宅等で治療に専念している状態も含まれます。
障害等級1級または2級に認定された状態
入院や在宅療養していなくても、障害等級1級または2級に認定された場合、就業不能状態とみなされる場合があります。
障害等級の1級と2級にあたるのは、以下の表の状態です。
| 障害等級 | 身体障害 |
|---|---|
| 第1級 |
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ・両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの ・上腕や下肢に著しい障害を有するもの ・座っていることができない、または立ち上がることができない程度の障害 など |
| 第2級 |
・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ・歩くことができない程度の障害を有するもの ・日常生活が著しい制限を受けるもの など |
- 参照:日本年金機構「障害等級表」(抜粋)
上記にあてはまり、医師の診断書と申請書により認められた場合に障害等級を与えられます。
②精神疾患は支払対象?
精神疾患により就業不能となった場合、就業不能保険の支払対象となる商品と、支払対象とならない商品があります。
なかには、精神疾患でも就業不能状態と認めることを特長としている就業不能保険もあり、加入前にしっかり確認しておく必要があるでしょう。
厚生労働省の「令和2年(2020)患者調査の概況」によれば、精神および行動の障害で入院している人は人口10万人あたり188人、外来211人。入院では他の傷病と比較し、最も高い受療率となっています。※1
どのくらいの期間、就業不能状態だったら支払われる?
保険商品や契約によりますが、一般的には30日、45日、60日といった日数で就業不能状態と診断されたら支払われます。
お支払条件は各社の就業不能保険あるいは契約内容によって異なるため、契約前に必ず確認しましょう。
就業不能保険の支払条件の例は?実際に支払対象となった事例もご紹介

ここでは、フコク生命の就業不能保障特約「はたらくささえプラス」のお支払条件や実際の事例を紹介します。
- ※「はたらくささえプラス」は特約組立型総合保険「未来のとびら」に付加できる特約です。
はたらくささえプラスのお支払い条件
「はたらくささえプラス」では、以下の状態に該当した場合、給付金および年金をお受け取りいただけます。
- 1. 就業不能状態(※1)が30日間継続した場合、就業不能給付金を12ヵ月にわたり毎月受け取れます。
- 2. 就業不能状態(※2)が1年間継続した場合、就業不能年金を生存しているかぎり70歳まで毎年受け取れます。
- (※1) 病気(精神疾患、妊娠・出産等にかかわるものを除く)またはケガによる入院または在宅療養(*1)、所定の精神疾患(*2)による入院。
- (※2) 病気(精神疾患、妊娠・出産等にかかわるものを除く)または、ケガによる入院または在宅療養(*1)。
在宅療養(*1)、所定の精神疾患(*2)の詳細説明は、よくある質問に記載されています。
はたらくささえプラスのお支払対象となった事例
お支払条件を踏まえ、実際に、就業不能保障特約「はたらくささえプラス」でお支払対象となった2つの事例を紹介します。
事例1. 就業不能給付金
被保険者:35歳男性
特約給付金月額:15万円
お支払総額:180万円
上記の事例では、90日間の入院と20日間の自宅療養をしており、お支払いの条件となる「就業不能状態が30日間継続」を満たしています。そのため、毎月15万円の就業不能給付金を1年間で合計180万円受け取れました。
事例2. 就業不能年金の例
被保険者:40歳男性
特約給付金月額:15万円
お支払総額:5,400万円(70歳まで生存した場合)
上記の事例は、90日間の入院と1年半の在宅療養をしており、就業不能状態が1年間継続」の条件を満たしています。そのため、毎月15万円の就業不能給付金を1年間で合計180万円受け取った後、就業不能年金を70歳まで毎年180万円受け取ることができます。
まとめ
2023年03月20日
カテゴリ
キーワード
資料請求・ご相談